錆の原因:防錆成分の無い油
堀口は1)以下のように言っている。
坊間良く潤滑油その他油類が防錆作用を有するかの如く誤認されているが、潤滑油自身の防錆力は弱く、空気より凝集した水分やその他固形物などは油層を通じて金属面に接触して錆を生じ、又腐蝕作用を呈するもので、例えば軸受けの防錆効果のあるものは発動機潤滑油には耐酸化性、耐熱性が少ないのでそのまま利用することは出来ないし、又超高圧に耐えるハイボイド油の如きは極圧性は強いが、そのために却って腐蝕作用が著しく進行し、金属加工油は用途に応じて潤滑性は良いが、特に乳化型では加工後の錆を誘発し、腐食を起こすなどの問題があって、防蝕防錆添加剤と潤滑性、作業性の問題は最近特に重視されている。
油は水よりも軽いから水の表面に浮かぶ。油を塗られた鉄鋼表面に水がつけば、水は油を押しのけて鉄表面に直接接触しサビが発生する。2)
菅沼は3)以下のように言っている。
大抵の人は水と油は混合しないという事を知っている。このことから推測して、もし金属が潤滑油でカバーされていると、水の金属への接触が油によって阻止されるから、水によろさびの発生は起こらないということが理解されよう。しかし実際には、潤滑油の比重は水よりも軽いため、水によって押しのけられるか、または水がその中を通り抜けて金属表面に接触して、さびを起こす事が多い。
また、大抵の金属は油よりも水のほうに大きな親和力をもっているから、金属面に水と油が共存すると、水のほうが油よりもよりよく金属面に保有される。
純粋の鉱油やグリースの持つ吸着性は、水、その他腐食要因の持つ同種の力よりも劣るので、結局、押し退けられて水の侵入を許してしまうのである。
山本は4)以下のように言っている。
油というものすべてが防錆性を有するのではない。一般に潤滑油といい、潤滑性をよくした油は、硫酸精製をしているため、硫酸分の残りがかえつて鉄を腐食させるものがあるので注意すべきである。
ボルト、ナットの圧造部品は、圧造加工と切削、熱処理が中心である。ここでは、硫黄、塩素系極圧剤を大量に配合した圧造油、切削油が使用され、加工部の発錆・腐食を招くケースが多い。5)
以上よりただの油では錆を防ぐ事ができない。場合によっては錆びやすくなる油もある。
錆の対策:防錆油または防錆成分を含む加工油の使用
参考文献
1)堀口博 著. 潤滑油とグリース, 三共出版, P395,1968
2)日本防錆技術協会 編『防錆技術便覧』,日刊工業新聞社,P286,1958.
3)菅沼豊 著『防錆包装技術便覧 : 防錆処理と個装の諸方式』,CPC研究所,P84~P86,1971.
4)山本洋一 著『金属防食技術の実際』,オーム社書店,P128~P129,1958
5)さびを防ぐ事典編集委員会 編. さびの発生原因と対策, 産業調査会出版部, P28,1984.9, (さびのQCシリーズ)

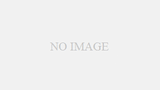
コメント